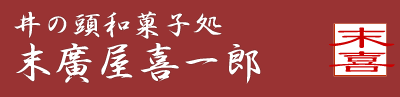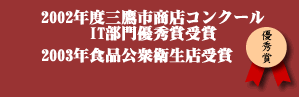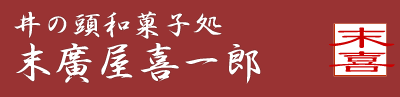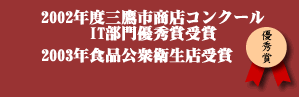人生と和菓子(簡易版)
 帯祝 帯祝
三韓征伐の時に、懐妊していた神功(じんぐう)皇后が、岩田帯を締めたという故事に習って、それを祝ったのがはじまりと言われています。五ヶ月目の戌の日から、この岩田帯を締めて、その喜びの気持ちを表すと同時に妊婦の健康、安産を祈願します。犬は多産で、お産が軽いので、それにあやかっていると言われています。
・お赤飯、鳥の子餅など
 お宮参り お宮参り
住んでいるところの氏神様に、氏子入りのご挨拶をすることをお宮参りと言います。男の子が32日目、女の子が33日目に、夫の母親が赤ちゃんを抱いて、氏神様に参詣します。最近では、赤ちゃんが幸せに育つことを祈願するという意味合いが強くなっています。
・紅白饅頭、鶴の子餅、鳥の子餅など
 初誕生 初誕生
子供の始めてのお誕生日に、一升餅を誕生餅として子供に背負わせます。子供の初めての誕生日を祝い、健やかな成長を祈るのです。子供に一升餅が大きい場合は、半分の大きさを2つ用意して、2回背負わせるところもあるようです。
・一升餅、赤飯など |
 |
|
 七五三 七五三
七五三が行われるようになったのは、江戸時代からと言われています。かつては、武家社会において子供の成長の節目ということで行われていました。男女共に3歳になると、短くしていた頭髪を初めて伸ばす儀式(三歳男女髪置祝)が行われ、男の子は、5歳になると、初めて袴を着ける儀式(五歳男子袴着儀式)、女の子は、7歳になると、初めて帯を用いる儀式(七歳帯解祝)として、生まれた土地の産土神社に、子供の福運を祝ってお参りするのです。また、千歳飴は長寿の願いが込められています。
・千歳飴、鳥の子餅、鶴の子餅、赤飯など |
 |
 入学・卒業 入学・卒業
わが子の入学や卒業は、親にとってこの上ない喜びとともに、子供にとっては、社会で生きていく節目にもなります。子供の新しい門出に、親子で、希望や思い出などをお話しながらお祝いをします。
・お赤飯、紅白饅頭など
 成人式 成人式
奈良時代以前から皇族や貴族の間では、男の子が15歳になると髪型を変え、烏帽子をつける「初冠」という儀式が行われてきました。これが、武家社会になると、冠をかぶり、幼名から成人の名前に変える「元服式」となり、江戸時代になると月代を剃る儀式となりました。女の子の場合は、加味を結い上げる「髪上げの儀」が成人を意味する儀式でした。昭和の戦前の時代には、男の子は徴兵検査、女の子は初初潮祝いが大人への仲間入りとされていました。昭和23年に1月15日を成人式とすることが定められ、満20歳になった男女を、この日から成人とし、選挙権や、結婚の自由などの権利が与えられ、社会人としての強い自覚と責任を認識することを課せられました。2000年から、祝日法の改正により、1月の第2月曜日が成人の日となりました。
・お赤飯、紅白饅頭他
 就職祝い 就職祝い
日本国憲法では、「納税」「教育」「勤労」が3大義務と定められています。憲法の上では、成人式をもって大人と認められるのですが、現在の実生活では、就職をし、親から巣立つことで大人と認められているのではないでしょうか?どちらにしても、その人にとって、新しい門出であり、それを祝うのです。
・お赤飯、桜や松竹梅の練り切りなど
 結婚 結婚
人の人生の大切な転機といえる結婚は、社会の最小単位である家族を作り、子子孫孫の反映の道を共に歩んでいくことを誓うとても大切な儀式です。周囲は惜しみなく彼らを祝福し、見守り、彼らは、これからの長い人生をともに白髪が生えるまで、寄り添って生きていくのです。
・紅白饅頭、共白髪、松竹梅の練り切りなど
 結婚記念日 結婚記念日
結婚記念日は夫婦の健在の証を祝います。5年目が木婚式、15年目が、水晶婚式、35年目が珊瑚婚式、45年目が紅玉婚式、50年目が金婚式、75年目が金剛石婚式です。このような、記念日を祝うことで、2人の結婚生活を振り返り、また、お互いの労をねぎらう節目とするのです。
・お赤飯、紅白饅頭、共白髪など
 長寿祝い 長寿祝い
わが国の中世から続いている長寿祝いは、61歳還暦、70歳古稀、77歳喜の字、80歳傘寿、88歳が米寿、99歳が白寿です。それぞれのお祝いに感謝の気持ちを添えて長寿をお祝いするのです。
・お赤飯、紅白饅頭、松竹梅鶴亀の練り切りなど
 敬老の日 敬老の日
「長年にわたり、社会に尽くしてきた老人に敬愛し、長寿を祝う日」が敬老の日とされました。1966年(昭和41)に「国民の祝日に関する法律」の改正により建国記念の日、体育の日とともに追加された国民の祝日です。敬老の日の由来は聖徳太子が四天王寺に悲田院(ひでんいん)を設立したと伝えられている日にちなみ、1951年からのとしよりの日が起源となっているようです。1964年からは老人の日とよばれ敬老行事が行われてきました。2001年(平成13)の改正により、2003年からは9月の第3月曜日に変更されます。また、老人福祉法の改正により、今年(2002年)から、9月15日を老人の日、同日から21日までを老人週間とされるそうです。
・お赤飯、紅白饅頭、松竹梅鶴亀の練り切りなど
 全快祝 全快祝
病気の時は、誰でも心細いものです。また、病気が治ったら、健康な体がどれほど大切かが改めてわかるのです。病気の全快と今後の健康を祈って全快祝をするのです。
・お赤飯、紅白饅頭、青梅など
(青梅)昔から薬用として食されていた青梅の実を模したお菓子。青梅が入っている場合もあり、その場合は、時期である6月のみお店に並ぶ。
▼感想はこちらまで。suehiro@sueki.jp
|