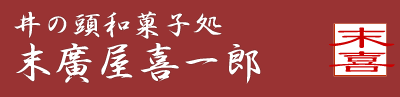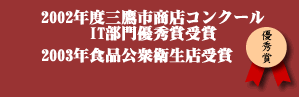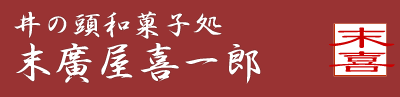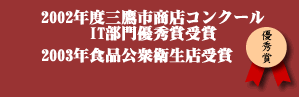|
1-1. もち米は一晩水につけておき、充分吸水させます
※指でつぶしてみて、ポロっと砕けて粉になったらOK
|
 |
2-1. 吸水させたもち米を布巾に広げます
|
 |
2-2. もち米を包み、すりこぎなどで叩いて米を砕きます
|
 |
3-1. さらに、こねるようにして揉みます
※この作業を「でちる」といいます
(^^)ちょっと調べてみたら、「でっちる」という方が一般的なようです。方言なのかな?
※手前から奥に、ぎゅっと転がすようにしてでちります
|
 |
3-2. 米粒の大きさは、1/2から1/4くらいがよいでしょう
|
 |
4-1. 枠に布巾を敷き、砕いたもち米をあけて平らにならし、約30分強火で蒸します
|
 |
もち米を蒸している間に、蜜とあん玉を作ります
5-1. 砂糖と水を合わせます
|
 |
5-2. 色粉を入れて、火にかけて軽く沸騰させます
|
 |
6-1. こしあんを、25gくらいずつ丸めます (大きさはお好みで)
※周りの生地が水っぽいのでやや固めに
→職人のアドバイス
(^^)こうやって並べると、数が数えやすいんですって!!アヤは何回聞いても覚えられません…(汗)
|
 |
※4-1.のもち米が蒸しあがりました (食べてみて芯がなければOK)
|
 |
7-1. 軽く沸騰している蜜に蒸しあがったもち米を入れます
|
 |
7-2. 軽く混ぜてなじませたら火を止めます
(^^)この時点では、水分びしゃびしゃです
|
 |
7-3. 濡れ布巾をかぶせて10〜15分蒸らし、もち米に蜜を吸わせます
※濡れ布巾は表面の乾燥を防ぐためです
|
 |
8-1. 「艶天(つやてん)」を溶かして手蜜を作ります
→職人のアドバイス
※艶天は家庭用に少しだけ作るのは難しいので、砂糖蜜を作ってください
|
 |
※7-2.が蜜を吸うと、こんな風にぼってりしてきます。びしゃびしゃだった水分は染み出てきません。
(^^)これが道明寺餅です!
|
 |
9-1. 7-2.のもち米が充分に蜜を吸ったら、軽く絞った濡れ布巾に取り、約30gずつに分けます。
|
 |
道明寺餅であん玉を包みます
10-1. 手蜜を手のひらに取り、道明寺餅を手のひらでたたいて平らに広げます
|
 |
10-2. あん玉を乗せます
(^^)指の付け根の辺りにくぼみを作って乗せると扱いやすいです
|
 |
10-3. 親指・人差し指・中指を使って時計回りにくるくる回しながら周りのお餅を少しずつ上方向へ伸ばし、綴じ目を閉じます
※上方向へ伸ばすのは親指の役目です
|
 |
10-4. 手のひらで軽く転がし、俵型に整えます
|
 |
10-5. 塩抜きした桜の葉を巻きます
※葉からはみ出している茎はとります
|
 |
☆☆☆ 出来上がり ☆☆☆
|